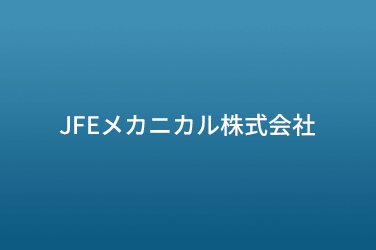EAM(Enterprise Asset Management:統合資産管理)プロジェクトの成功は、優れたシステムを導入するだけでは実現できません。各部門が個別に取り組むのではなく、経営層・現場・IT部門が一体となって取り組むことが不可欠です。経営層のリーダーシップの下で、現場の知見とITの技術力を結集することで、EAMは初めて企業価値を高める基盤となります。
本記事では、EAM導入を成功に導くために必要な体制構築と、経営層・現場・IT部門それぞれの役割について解説します。
実際にEAMを導入して変化を遂げた、現場のリアルな動きを詳しく知りたい方はダウンロード資料をご活用ください。
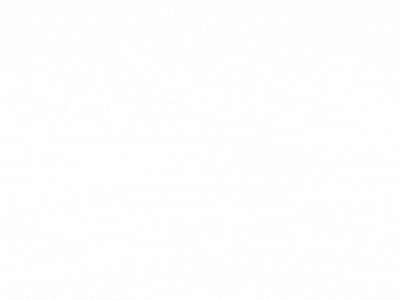
設備保全のいまを変える
EAM活用事例
事例を見れば、EAM導入によるメリットがわかる!予知保全と技術伝承を同時に解決する具体的な方法を提供します。
現場任せの限界と、経営の関与が求められる時代へ
製造業における設備管理は長らく、「故障が発生したら現場で対応する」といった属人的な手法に頼ってきました。こうした現場依存の運用で大きな問題が表面化せずに済んでいた背景には、経験豊富な技術者の存在や、比較的安定した市場環境がありました。
しかし今、状況は大きく変わりつつあります。熟練技術者の引退が進む一方で、ノウハウの継承が追いつかず、現場対応の限界が顕在化しています。同時に、グローバル競争の激化や事業継続性への要求の高まりから、設備管理にも安定稼働やコスト最適化、リスク低減といった経営視点での高度な対応が求められるようになっています。
このような時代において、単にコストを抑えたミニマムな現場効率化を求めるシステムを導入しても、真の課題解決にはつながりません。いまやEAMは、単なる現場支援ツールではなく、企業の競争力を左右する戦略的インフラになりつつあります。だからこそ、経営層が正面から関与し、組織横断での本格的な取り組みを進める必要があるのです。
経営層がなぜEAMに本気で向き合うべきか
EAMは、現場の業務効率化にとどまらず、企業の経営基盤を安定させるための重要な投資です。しかし、そのポテンシャルを最大限に引き出すためには、経営層の深い理解とコミットメントが不可欠です。
もしEAMの運用が現場任せになってしまうと、次のような経営に直結するリスクを抱え込むことになります。
-
機会損失リスク:設備トラブルによる生産ラインが停止し、納期遅延や顧客離れにつながる
-
収益圧迫リスク:計画外の高額修繕費が発生し、企業の利益を圧迫してしまう
-
技術伝承リスク:現場のノウハウが標準化されず、ベテラン頼みの属人的な保全が続けば、品質の低下やミスの増加は避けられない
-
社会的リスク:大規模な障害や災害が発生した場合に生産性リスクだけではなく、対外的・社会的な信頼を損なうことにつながる
これらのリスクを軽視し、経営が「システムは導入したから、あとは現場で」という姿勢でいると、現場は「経営が望む指標や本来の目的を満たす方向に進まない」「何のために導入したかというDNAが継承されず、個々の判断によりシステムの活用にバラツキがある」という状況に陥ります。その結果、システムは形骸化し、「高価なシステムを導入したのに、全く使われない」「期待したほどの導入効果が得られない」という、典型的な失敗パターンに陥ってしまうのです。
経営層の関与が不可欠な理由
なぜ、経営が主体的にEAMに向き合う必要があるのでしょうか。その理由は大きく3つに整理できます。
- 1.
-
複数部門にまたがる全社横断プロジェクト
EAMは、設備保全・IT・調達・財務など複数部門にまたがる全社課題であり、部門間の調整に経営の権限が必要です。例えば、設備データの統一化には、保全部門の現場知見とIT部門の技術力、さらに予算承認のための財務部門との連携が不可欠です。各部門が個別最適を追求すると、システム仕様や運用ルールに矛盾が生じ、結果的に誰も使わないシステムが完成してしまいます。経営層が旗振り役となり、全社最適の視点で部門間の利害調整を行うことで、真に機能するEAMが実現できます。
- 2.
-
中長期的な投資判断が求められる
投資効果が短期では見えにくく、中長期的視点での判断が求められます。EAM導入による効果は、故障率の低下や稼働率の向上といった形で現れますが、これらの成果が数値として明確になるまでには一定の期間を要します。EAMの導入によって、現場の情報が統合管理でき、適切な業務フローを形成する定性的な効果や、情報の蓄積による保全周期の健全性評価、保全コストの最適化が可能になります。経営層は、これらの効果を中長期のスパンで投資対効果を評価することが重要です。
- 3.
-
現場の変化に対する経営の積極的支援
導入による現場オペレーションの変化に対し、経営層が積極的に支援・発信することで定着を促進できます。EAM導入により、従来の紙ベースの管理からデジタル管理への移行や、定性的な判断から定量的な意思決定への変化が求められます。現場作業者にとっては慣れ親しんだ業務フローの大幅な変更となるため、抵抗感や不安が生まれることは避けられません。一方で、システムに蓄積した情報を指標(KPI)化することで経営層と現場の共通の課題認識を行うことができ、今の活動の成否を見極めることができるようになります。経営層が定期的に現場の状況を把握し、EAM活用の意義を直接説明し、改善提案を積極的に評価することで、現場の意識変革と主体的な取り組みを促すことができます。
EAM導入で失敗しがちな典型パターン
EAM導入にはさまざまな落とし穴があります。代表的な失敗パターンを以下に紹介します。
経営層の理解不足による過小投資
経営層のEAMに対する理解不足から、費用を抑えた限定的な導入に留まるケースがあります。こうした判断は、現場の実情に合わないシステムを招き、十分に活用されないまま終わる可能性が高まります。本来EAMは、設備情報の管理にとどまらず、企業の資産戦略を支える基幹的な仕組みです。この資産戦略の重要性についてはISO55000シリーズでもAsset Managementが定義されており、準拠する運用が不可欠となります。機能が不十分なまま導入すれば、かえって業務効率が低下し、運用負荷や再構築コストが増すリスクもあります。導入において重要なのは、初期段階から必要要件を見極め、中長期的な拡張性を見据えて適切に投資することです。短期的なコスト削減を優先するか、将来の価値を重視するかが、成否を左右します。
現場とIT部門の認識ギャップ
現場とIT部門の間で要件の認識にズレがあり、机上の空論になってしまいます。IT部門は技術的な完成度を重視する一方、現場は日々の作業効率を最優先に考えます。この視点の違いが十分に調整されないまま開発が進むと、高機能だが使いにくいシステムや逆に現場特化しすぎて拡張性のないシステムが生まれます。要件定義段階での密な対話と、プロトタイプによる早期検証が、認識ギャップの解消には不可欠です。 特に、マスターデータ登録や項目名称の標準化において、現場担当者にとって分かりやすく使いやすい設計にするための認識合わせに多くの時間を要するケースがあります。デモ環境での操作体験を通じてシステムを利用する際のイメージや、システムを活用することで、どのように業務上の効果が生まれるのかを事前に検証することが、このギャップを埋める有効な手段となります。また、システムの利用開始時の業務変化に対してどれだけ現場を支援していく体制がとれるかも定着への大きなキーポイントとなります。
推進リーダーの権限不足
専任の推進リーダーがいないことで、関係部門の協力を得られず、プロジェクトが立ち行かなくなります。EAMプロジェクトは複数部門の利害が絡むため、調整役には強い権限と専任の時間が必要です。兼務でプロジェクトを進めようとすると、日常業務に追われて重要な判断が後回しになり、結果的にプロジェクトの進捗が停滞します。経営層から明確な権限委譲を受けた専任リーダーの配置が、スムーズな推進の前提条件です。
導入後の改善活動停滞
システム導入で満足し、その後の改善活動が止まると使われない仕組みになります。EAMの真価は導入後の継続的な改善活動にあります。しかし、多くの企業では「システムが稼働した」時点でプロジェクト完了と捉え、その後の運用改善やデータ活用に対する関心が薄れてしまいます。定期的な効果測定と改善サイクルを仕組み化し、EAMを育て続ける体制の構築が持続的な成果につながります。昨今では、分析(BI)やAIの活用を視野に入れた活動が増加しているように、蓄積した情報の価値が大きくなっています。 記録データを活用した改善を促すことは、今後の業務を支えていくことに不可欠です。
導入を成功に導く経営層・現場・IT部門の役割
EAM導入を成功させるためには、体制構築がすべてといっても過言ではありません。特に、経営層、現場、IT部門それぞれが明確な役割を理解し、適切に連携することが重要です。
経営層の主な役割:強力な推進力とリーダーシップ
経営層は、EAM導入プロジェクトの成功を左右する最重要ポジションです。プロジェクト全体の方向性を決定し、部門間の意見を調整する積極的な役割を担います。
エグゼクティブスポンサーとしての責任と権限の明確化
EAM導入の意義を全社に対して繰り返し発信し、現場の不安や抵抗感を乗り越える推進力となることが求められます。単なる承認者ではなく、戦略的な方向性を示し、重要な局面では自ら判断を下す"プロジェクトの最終責任者"としての姿勢が不可欠です。プロジェクトの成功には、専任人材の確保とともに、必要なリソースを適切なタイミングで投入する意思決定が求められます。限られた予算や人員の制約を理由に、現場へ過度な工夫を求めるのではなく、企業全体の価値創出に見合った投資として捉える視座が重要です。
専任プロジェクトリーダーの配置と権限設定
EAM導入を成功に導くためには、専任のプロジェクトリーダーを配置し、部門を横断して調整・統率するための明確な権限と責任範囲を付与することが必要です。具体的には、他部門への調整権限、実行判断に必要な予算管理機能、意思決定を伴う指示権限などを体系的に整備します。
プロジェクトリーダーの発信に実効性と緊急性を持たせることで、部門間における業務負荷や優先順位の調整をスムーズに進めることが可能になります。"全社最適"の視点で迅速かつ一貫性のある判断を下せる体制整備が、推進力の源泉となります。 また、リーダーには部門横断的な知見やリレーションシップを持つメンバーの配置が円滑なコミュニケーションを支えるキーポイントです。
部門間の役割分担と責任範囲の明文化
各部門がEAMプロジェクトにおいてどのような役割を担い、どこまで責任を持つのかを明確に定義し、社内で正式に合意形成することが必要です。設備保全部門は現場での実運用とデータ収集、IT部門はシステム開発と技術的サポート、調達・財務部門は各々の専門領域での連携といったように、責任範囲を明確化することで、「誰が判断するのか分からない」という停滞を防ぎます。
現場の声を継続的に吸い上げる仕組みの構築
EAM導入の本質は、"現場に根付く仕組み"として機能することにあります。経営層は、現場からの課題や改善要望がプロジェクトに迅速に反映されるよう、定例会議や双方向のフィードバック体制など、継続的な情報共有の仕組みを整備する必要があります。
月次の経営会議などでプロジェクト進捗を恒常的に議題化し、IT・現場双方からの声を直接受け止める機会を設けることで、現場との信頼関係を構築しながら、着実な推進を支えることが可能になります。
現場部門の主な役割:実運用の要件定義と定着推進
現場部門はEAMシステムの最大の利用者であり、成功の鍵を握る重要な存在です。実際の業務を熟知している現場だからこそ、システムの実用性と効果を最大化する役割を担います。
現状業務の詳細な洗い出し
既存の保全業務プロセス、課題、改善要望の整理を行います。単なる作業手順の列挙ではなく、なぜその手順が必要なのか、どこに無駄や非効率があるのかを現場目線で具体的に分析し、システム化によって解決すべき真の課題を明確にします。
要件定義への積極的参画
実際の作業フローに基づいた機能要件の明確化を行います。IT部門が提示する仕様に対して「使えるか使えないか」を判断するだけでなく、法規・内規に沿った業務プロセスの遵守を考慮しつつ、現場の実情を踏まえた代替案の提示や、業務効率化につながる新たな機能要望を積極的に発信します。
システム導入後の運用改善
継続的なフィードバックと業務プロセスの改善を行います。「システムが使いにくい」で終わらせるのではなく、具体的な改善提案を継続的に提供し、現場に根付くまで粘り強く取り組みます。小さな改善の積み重ねが大きな成果につながります。
IT部門の主な役割:技術基盤の構築と現場との連携
IT部門は、現場ニーズを理解した実用的なシステムの構築と、長期安定運用の技術基盤整備を行う役割を担います。
技術要件の整理と実現可能性の検証
現場要望の技術的実現方法の検討を行います。現場から出される「こんなことはできないか」という要望に対して、技術的な制約や実現のための工数・コストを正確に見積もり、代替案も含めて現場に分かりやすく説明します。できることと、できないことの線引きを明確にし、その上で最も効果的な解決策を共に探す姿勢が大切です。
システム設計・開発・テスト
堅牢で使いやすいシステムの構築を行います。技術的な完璧性だけでなく、現場での実際の使い勝手を重視した設計を心がけ、操作性の検証を現場と連携して実施します。また、段階的なリリースにより早期に動作確認できる環境を提供し、現場からのフィードバックを開発に反映させます。
他システムとの連携設計
既存の生産管理システムや財務会計システムなど、社内で運用されている各種システムとのデータ連携を前提とした設計を行います。重複入力や情報の分断を防ぎ、業務全体の整合性と効率性を高めるために、データ項目の標準化や連携タイミングの設計などを丁寧に検討します。
経営層・現場・IT部門の連携方法
EAM導入プロジェクトでは、部門間の連携不足が失敗の大きな要因となります。ここでは、効果的な会議体制の構築と、経営層による部門間調整機能について具体的に解説します。
会議体制の整備
部門間の継続的な対話と迅速な意思決定を支えるため、以下のような会議体を設けることが有効です。
| 会議名称 | 参加部門 | 開催頻度 | 主な目的・役割 |
|---|---|---|---|
| 経営層会議 | 経営層、プロジェクト責任者、代表者 | 月1回 | 全社方針・予算の決定。現場・IT部門からの課題報告を受け、方向性の修正や追加投資の可否を判断。プロジェクトへの経営層のコミットメントを示す場としても機能。 |
| プロジェクト会議 | 現場、IT部門、プロジェクト責任者、必要に応じて経営層 | 週1回 | 進捗確認、課題共有、技術的検討。部門間の優先順位や認識のズレを調整し、迅速な対応を可能にする。 |
| 現場フィードバック会議 | 現場担当者、IT部門 | 月2回〜 | システムの使い勝手や改善要望を現場から直接共有。IT部門は技術的な実現可否や対応スケジュールを提示し、現場との継続的な対話を促進。 |
このような多層的な会議体制を整えることで、現場・IT・経営層の連携を密にし、課題の放置や部門間の齟齬を未然に防ぐことが可能になります。
経営層による効果的な意思決定と調整
技術的制約と現場ニーズのバランス調整
現場からの要求とIT部門の技術的制約が対立する場合、経営層は全社的な視点から優先順位を判断し、必要に応じて代替案の採用や追加リソースの投資を決定します。これにより、停滞の回避と現場の納得感を両立させることが可能になります。
全社最適に基づくリソース配分
複数部門でリソース競合が発生した際には、経営層が企業全体の戦略的優先順位を明確にし、適切な人員配置や業務の優先度変更を行います。これにより、EAMプロジェクトが他業務と衝突するリスクを低減し、全社最適の観点から推進を図ります。
適切な会議体制と経営層のリーダーシップが連動することで、EAM導入プロジェクトは三位一体の連携体制のもと、円滑かつ確実に前進させることが可能となります。
経営層・現場・IT部門の一体化が成功の鍵
EAM導入の成否は、経営層・現場・IT部門の明確な役割分担と密接な連携によって決まります。経営層は強いリーダーシップのもとで専任体制を構築し、部門横断的な調整を主導します。現場部門は、実業務に即した要件定義と継続的なフィードバックにより、システムを実用的かつ現場に根付くものへと育てます。IT部門は、現場のニーズを的確に把握した上で、技術的な実現と長期的な安定運用の基盤を担保します。
この3部門が、定期的な会議体制のもとで継続的な対話を重ねながら連携することで、EAMシステムは業務に深く根付き、実効性のある運用が実現されます。
従来のように、現場任せで断片的に対応したり、コスト優先で機能の限定されたシステムを導入したりするアプローチでは、EAMの真価を引き出すことはできません。経営層・現場・IT部門が共通の目的を掲げ、戦略的に一体となって取り組む体制こそが、成功への鍵となります。
このような適切な体制構築と確実なEAM導入プロジェクトの実現に向けて、保全業務を熟知したエンジニアがご支援するエクサの"IBM Maximo導入支援サービス"がサポートいたします。
また、エクサ独自のEXA Base Kit(短期導入ソリューション、旧Maximo Base Kit)により、導入初期段階から実際に稼働するシステムを確認でき、部門間の認識ギャップを解消します。また、段階的教育プログラムと継続的な現場サポートにより、システム稼働後の自主運用まで責任を持ってサポートします。
JFEスチールグループの一員として、製鉄所で培ってきたシステム運用ノウハウと、40社以上の豊富な導入実績を活かし、適切な投資規模でのEAMの導入を実現します。
IBM Maximoに関する詳細な情報については、以下をご覧ください。
IBM Maximoソリューション(株式会社エクサ)
EXA Base Kitを実際に導入した事例は以下をご覧ください。
【導入事例】全国スキー場のリフト、圧雪車、降雪機の保全管理システムをIBM Maximoで構築|JFEプラントエンジ株式会社様
関連する記事
関連ソリューション
関連事例
お問い合わせ
CONTACT
Webからのお問い合わせ
エクサの最新情報と
セミナー案内を
お届けします