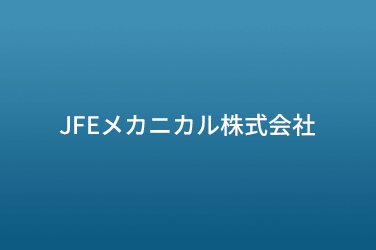突発的な設備停止は、生産計画の乱れや納期遅延、取引先からの信頼低下、作業者の負担増加など、企業全体の事業活動に直結する重大なリスクです。さらに、復旧対応にかかるコストや代替手配による追加負担も発生します。
本記事では、設備故障が企業にもたらすリスクをあらためて整理し、"止めない現場"を目指した保全の在り方について解説します。
設備故障が企業に与えるリスクの現実
製造現場における設備故障は、予兆の有無に関わらず企業経営に深刻な影響を与えるリスクです。現場では主に2つのパターンで故障が発生する傾向があります。
ひとつは、設備異常の兆候を把握していても、判断や対応が後手に回り、設備トラブルに発展するケースです。現場では設備の微細な変化を作業者が感じ取れる場面もありますが、それらを正確に判断し、迅速な保全対応へと結びつける体制が整っていないのが実情です。こうした課題の背景には、保全情報が一元管理されていないことがあります。データ形式の不統一や保管場所の分散により、設備情報の有効活用が困難になっているのが実情です。
もうひとつは、定期点検や日常の管理を適切に行っていても、経年劣化や想定外の要因により突発的に発生する予期せぬ故障です。設備の老朽化が進む中、これまでに見られなかった新たな不具合の発生や、ベテラン技術者の知見に依存した属人的な判断体制、人手不足による点検頻度の制約なども、予期せぬ故障のリスクを高める要因となっています。
従来の保全手法では対応しきれない現実があり、新たな保全戦略が求められています。
設備故障による損失の実例
設備故障による損失がどれほど大きな影響を与えるかを、実際に発生した2つの事例から見ていきます。
事例1:設備火災による甚大な損失
2020年10月、旭化成エレクトロニクス延岡事業所の半導体製造工場で大規模火災が発生しました。
事故の詳細
- 原因:約20年間使用の未反応チタン除去装置で、端子部の接触不良や半断線による発熱・発火
※この原因は、被災現場での装置確認が困難であり、類似装置を用いた検証に基づく推定であり、確定的なものではありません - 被害規模:FAB棟4階・5階の広範囲焼損、屋根一部崩落
- 鎮火まで:約92時間(4日間)の長期火災
設備火災による損失の全体像
- 生産装置・検査装置の焼損:広範囲にわたる設備の焼損
- 建屋・インフラ被害:FAB棟の大規模改修・再建が必要
- 仕掛品・製品在庫:クリーンルーム内の仕掛かり製品も広範囲にわたって焼損
- 復旧期間:工場復旧の目途は立たず、事業継続に重大な影響
- 追加コスト:瓦礫撤去、環境対策
なお、旭化成株式会社の2021年3月期決算説明会によると、本火災による2020年度の損失額は合計223億円とされており、特別損失として一部が処理されています。損失には焼損した設備や製品に加え、瓦礫撤去、環境対策などの関連コストが含まれています。
この事故で特に注目すべきは、装置は法令に基づく定期点検を実施していたにも関わらず、火災を防げなかったという点です。3年ごとの電気保安点検は実施されており、直近の2019年の点検でも異常は確認されていませんでした。
事例2:過電流による火災で業界全体に波及
2021年3月にルネサス セミコンダクタ マニュファクチュアリング株式会社の那珂工場で発生した火災事故です。
事故の詳細
- 原因:N3棟(300mmライン)のめっき装置で過電流が発生し発火
※事故発生当時から現在に至るまで、原因の詳細に関する公式な続報は確認されていません - 被害規模:焼損面積約600㎡(クリーンルーム面積の約5%)、製造装置23台焼損
- 鎮火まで:約5時間25分
設備火災による損失の全体像
- N3棟の生産停止による売上影響:月当たり約130億円の売上減少(当初発表では170億円とされていたが、後に130億円に修正)
- 復旧に向けた対応:焼損した23台の製造装置の調達(当初発表では11台とされていたが、後に23台に修正)
※装置の交換・修理費用についての具体的な金額は未公表。 - クリーンルームの復旧:約600㎡の焼損が発生し、清掃作業を実施
- 代替生産:生産品目のうち約3分の2は代替生産が技術的に可能
※ただし、需給逼迫の影響により、即時の代替は困難な状況。 - 業界への波及:半導体需給が逼迫する中での事故であり、広範な影響が懸念される
出典元:
1:半導体製造工場(那珂工場)の火災発生に関するお知らせ
2:半導体製造工場(那珂工場)の火災発生に関するお知らせ(第二報)
3:半導体製造工場(那珂工場)の火災発生に関するお知らせ(第三報)
4:半導体製造工場(那珂工場)の火災発生に関するお知らせ(第四報)
5:半導体製造工場(那珂工場)の火災発生に関するお知らせ(第五報)
6:半導体製造工場(那珂工場)の火災発生に関するお知らせ(第六報)
これらの事例では、設備に起因する火災により甚大な損失が発生しました。旭化成の事例では定期点検を実施していたにも関わらず20年間の使用による経年劣化で火災を防げず、ルネサスの事例では突発的な過電流により火災が発生しており、従来の保全手法だけでは対応しきれないリスクの存在を示しています。
予知保全は止めない経営のための戦略投資へ
これらの深刻な事例を踏まえると、従来の壊れてから直す事後保全や、定期的な点検だけに頼った保全では、企業を取り巻くリスクに対応しきれないことが明らかです。
旭化成エレクトロニクスの223億円やルネサス セミコンダクタ マニュファクチュアリングの月130億円の売上減少という数字が示すように、設備故障による損失は企業経営に致命的な影響を与える可能性があります。では、こうしたリスクを最小化し、"止めない現場"を実現するためには、どのような保全戦略が必要なのでしょうか。
求められているのは、設備保全に対する根本的な発想の転換です。
保全を"コスト"から"経営判断"へ転換する必要性
従来、設備保全は守りのコストとして捉えられ、可能な限り削減すべき費用と位置づけられがちでした。しかし、先の事例で示したように、設備故障による損失は数百億円規模に達する可能性があります。この現実を前にすると、保全費用を単なるコストではなく、巨額の損失を防ぐための投資的判断として再定義する必要があります。
経営戦略としての保全投資の価値
設備保全への投資は、設備故障による直接的な損失を防ぐだけでなく、生産性の向上、品質の安定化、納期遵守率の向上など、企業の競争力を直接的に高める効果があります。現場の保全活動の中長期計画・予算化を実施することで経営層が設備保全の価値を正しく理解し、適切なリソースを配分し、止めない現場を実現することで、持続可能な企業成長を支える基盤を構築できます。設備保全は、企業の未来を支える経営判断の中核として見直されつつあります。
保全への投資を"経営判断"と位置づけるなら、適切なシステムの選定も重要な観点です。 EAMとCMMSの違いを整理したガイドBOOKで、自社に合った選択のポイントをご確認ください。
止めない現場を支える予知保全
保全の中でも、注目されているのが予知保全の導入です。予知保全は、トラブルが起こりそうな兆候を察知して保全を行う手法であり、AIなどのデジタル技術を活用することで実現します。
従来の壊れてから直す保全から、壊れない為の予防保全や状態保全の充実、故障する前に設備の声を傾聴し、予め対応する予知保全へと段階的に移行することで、"止めない現場"の実現が可能となります。
デジタル技術による予兆検知の実現
予知保全では、設備にIoTセンサーを設置し、稼働情報(音、振動、温度、圧力、電流など)をリアルタイムで収集・蓄積します。収集された膨大なデータをAIが分析し、故障の予兆や異常パターンを自動検知することで、「あと〇日で故障する可能性が高い」といった具体的な予測を提供できます。
これにより、人が立ち入れない危険な場所での点検作業を代替し、人の目や勘では見落とされがちな微細な変化をデータとして正確に把握できるようになります。
定期点検だけでは予見できない事象において、予兆検知に基づく先回り対応への移行が可能になります。
予知保全を実現するための統合管理とデータ活用
予知保全の効果を最大化するためには、単にセンサーでデータを収集するだけでは不十分です。収集したデータを有効活用し、故障パターンを的確に分析するための仕組みが必要となります。
統合管理による故障パターンの分析
統合資産管理(EAM)システムにより、設備台帳、保全計画、作業指示書、故障報告書、資材在庫などの保全関連情報を一元管理できます。これにより、過去の故障パターンと現在の設備状態を関連付けて分析し、故障の発生傾向を把握できるようになります。
従来の設備ごと、担当者ごとの分散した情報管理では、同じような故障を繰り返してしまう可能性があります。しかし、統合管理により全設備の故障履歴と保全記録を横断的に分析することで、「この設備でこの症状が出ると、数ヶ月後に故障する可能性が高い」といった予兆パターンを発見し、突発的な故障を未然に防ぐことが期待できます。
安定稼働とコスト最適化
データに基づく予知保全を導入するには、まず管理対象設備のリスク評価と優先度付けが必要です。ユニットや設備ごとに故障時のインパクトを評価し、どこに注力すべきかを組織内で精査します。これにより、過剰な対応や欠落していた保全を見直すことができます。この活動を経て予知保全を実施することで、ダウンタイムの削減と安定稼働につながり、突発的な故障による生産ラインの停止を大幅に削減することができます。
また、不要な部品交換費用や緊急対応に伴う割増人件費といったコストを削減し、適切なタイミングでのメンテナンスにより設備の寿命延長にもつながります。
さらに、AIによる異常予測や故障箇所特定により業務品質が向上し、危険な場所での作業をセンサーが代替することで作業員の安全性も大幅に向上します。予知保全の導入により、これまで避けられないと考えられていた設備故障による損失を、計画的に予防することが可能となります。
設備保全を経営戦略に位置付ける
日々の生産活動を支える設備の安定稼働は、企業全体の競争力に直結する要素です。
そのため、設備保全は単なる現場任せの対応ではなく、経営層が戦略的に意思決定すべき領域となりつつあります。デジタル技術を活用した予知保全の導入や、保全体制の再構築を通じて、リスクの未然防止とともに、安定した生産体制の実現が期待されます。
設備保全を経営戦略の一環として明確に位置づけることで、突発的な停止の抑制、納期遵守の向上、品質の安定化といった成果を中長期的に実現することが可能になります。
関連する記事
関連ソリューション
関連事例
お問い合わせ
CONTACT
Webからのお問い合わせ
エクサの最新情報と
セミナー案内を
お届けします