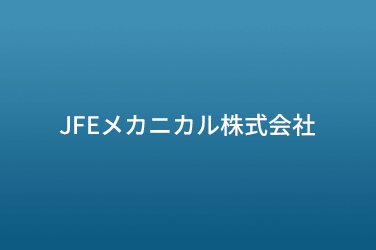製造現場で長年培われてきた熟練技術者のKKDと言われる勘や経験、度胸といったこれらの貴重な暗黙知が、ベテラン技術者の退職とともに失われつつあります。
この記事では、デジタル技術を活用してこうした暗黙知を可視化・体系化し、組織全体で共有する具体的な方法を解説します。
熟練技術者の暗黙知を見える化する取り組みを成功させるには、 どのシステムを選ぶかが最初の大きな分岐点となります。詳しく知りたい方はダウンロード資料をご活用ください。
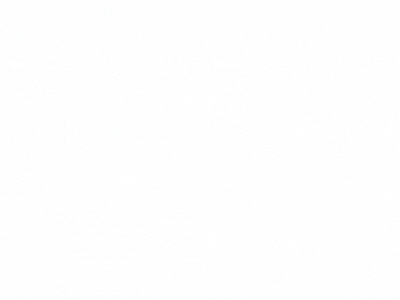
EAMとCMMSの違いを理解するガイドBOOK
EAMとCMMSの機能や特長の違いを整理し、企業規模や業種、管理対象設備の特性に応じた最適なシステム選定基準について解説します。
熟練技術者の技術継承における現状と課題
製造業では、団塊世代の技術者の世代交代により技術継承が重要な経営課題となっています。2024年版ものづくり白書の『令和5年度 ものづくり基盤技術の振興施策』によると、製造業において能力開発や人材育成に問題があると回答した事業所の割合は2022年度で82.8%に達し、全産業よりも高い割合となっています。問題点の詳細を見ると、「指導する人材が不足している」が61.8%と最も高く、製造業における技術継承の深刻な現状が浮き彫りになっています。
特に設備保全の現場では、長年の経験を持つ熟練技術者が音の違いや振動の感触で設備異常を察知する能力を発揮してきました。「この音は普通じゃない」「なんとなく調子が悪そう」といった経験と勘に基づく判断は、これまで多くの設備トラブルを未然に防いできました。
しかし、技術継承や人材育成に関する課題が指摘されており、この暗黙知に依存した保全業務には改善すべき課題があります。
主な課題
- 技術者によって判断基準が異なる場合がある
- 知識の属人化により組織全体の保全レベルにばらつきが生じる
- 人材不足の中で、若手技術者が感覚的な技術を習得するには長期間を要する
- 予防保全の精度向上に限界がある
これらの課題を解決する手段として、デジタル技術の活用が注目されています。IoT技術やAI、データベース活用により、これまで言語化が困難だった熟練者の知識を可視化し、組織全体で共有できるようになります。デジタル化により、技術継承の効率化、予防保全の精度向上、設備稼働率の改善が期待できます。
暗黙知をデジタル化する3つのアプローチ
ベテランの技術や知識をデジタル化し、組織全体で共有するための実践的な3つの方法をご紹介します。
1. データの一元管理と可視化による知識の形式知化
EAMシステムによる情報統合
熟練技術者が長年蓄積してきた保全ノウハウは、多くの場合、個人の頭の中や紙の記録、Excelファイルなどに分散して保管されています。これまで属人的であった保全履歴や設備状態情報をデジタルデータとして一元管理し、熟練者の記憶に頼っていた情報管理から、誰もがアクセス可能な知識共有システムへの転換を実現します。
EAM(Enterprise Asset Management:統合資産管理)システムを活用することで、設備台帳や保全計画、作業履歴、故障記録、部品情報などの膨大な情報を統合的に管理できます。これにより、「あの時どんな対応をしたか」「同じような症状の設備はないか」といった熟練者の記憶に依存していた情報検索が、誰でも瞬時に行えるようになります。
さらに、可視化されたダッシュボードにより、設備の稼働状況、保全実績、コスト分析などが一目で把握でき、経験の浅い技術者でも、ベテランと同等の判断基準で作業できる環境を整備できます。
2. AI・IoTによる故障予知と異常の早期発見
センサーデータ活用と予知保全
設備から発生する「いつもと違う音」や「異常な振動」といった微細な変化を、IoTセンサーとAI技術で数値化・可視化します。設備にIoTセンサーを設置してリアルタイムで稼働情報を収集し、AIによる予測モデルで故障の予兆を察知することで、感覚的な判断を定量的な監視システムで補完し、計画的保全を実現します。
具体的には、振動センサー、温度センサー、圧力センサー、電流センサーなどを活用して設備の状態を24時間365日監視し、正常値からの逸脱や異常パターンを自動検知します。AIが過去の故障データと現在の状態を照合することで、「あと◯日で故障する可能性が高い」といった具体的な予測を提供できます。
この仕組みにより、熟練者でなくても設備異常の予兆を早期発見でき、予防策や改善に向けた計画的なメンテナンススケジュールの立案が可能になります。また、突発的な故障による生産停止リスクを大幅に削減し、安定した操業を維持できます。
3. デジタルツールを活用した現場支援と技術継承
AR・ウェアラブル技術の活用
熟練技術者の技やコツといった暗黙知を、デジタル技術で可視化し継承する方法です。熟練度の低い作業者に対してAR遠隔支援を提供し、ウェアラブルカメラやスマートグラスで熟練者の目線や作業手順を映像として記録・共有することで、効率的な技術継承を実現します。
AR(拡張現実)技術を活用すれば、現場作業者がスマートグラスを装着するだけで、熟練者が作成した作業手順書や注意点、過去の故障事例などがリアルタイムで視野に表示されます。また、遠隔地にいる熟練技術者が現場の映像を見ながら、音声や画面上の指示で若手技術者をサポートすることも可能です。
さらに、ウェアラブルカメラで熟練者の作業を記録し、「どこを見ているか」「どのタイミングで判断しているか」「どんな手順で作業しているか」といった暗黙知を映像として蓄積できます。これらの映像資料は、新人研修や技術継承の貴重な教材として活用でき、熟練者が退職した後も組織内でノウハウを共有し続けることができます。特に、熟練者がオフショア(海外拠点)から支援できるようになることで、熟練者の働き方改革にもつながり、肉体的負担を減らしながら、その豊富な経験を多くのメンバーに還元する取り組みとなります。
デジタル化に成功した企業の取り組み事例
多くの産業が熟練技術者の退職に伴う技術継承の課題に直面しています。ここでは、デジタル技術を活用して暗黙知の形式知化に成功し、技術継承の課題を解決した企業の事例をご紹介します。これらの事例は、属人的だった保全業務をデータに基づく標準的な業務へと変革した成功例として参考になります。
麻生セメント株式会社:熟練者不足による技術継承課題の解決
課題
創業140年以上の歴史の中で、主要工場における熟練者不足が顕著となり、従来の設備管理手法が限界に達していました。部署や担当者ごとにバラバラに管理されていた文書や保全履歴、設備状態情報により、熟練者の退職後の技術継承が困難な状況でした。現場では紙で点検結果を記入したり、口頭での修理依頼やExcelへの転記といった属人的な業務プロセスが課題でした。
取り組み
統合資産管理システムを導入し、データに基づく保全業務の実現を目指しました。設備台帳や保全計画、故障報告書、作業指示書などの保全関連情報を一元管理し、タブレット用のモバイルアプリを開発して現場に導入を進めました。IoTやドローンなどの先進技術を活用した次世代の設備保全を見据えた基盤を構築しました。
成果
- 保全関連ドキュメントの共有基盤を構築し、情報の散在化を解決
- 報告・依頼業務をデジタル化し、紙ベースの業務から脱却することで情報共有を効率化
- 作業進捗の可視化機能で業務管理と見通しを改善
- データ蓄積による客観的な分析で、計画的保全(予知保全)を実現
事例の詳細は、以下よりご覧いただけます。
導入事例:麻生セメント株式会社
住友ファーマ株式会社:属人的な保全業務の標準化を実現
課題
止まらない工場と生産性向上を目指す上で、鈴鹿工場では標準化されていなかった設備保全業務と紙ベースの情報管理からの脱却が課題でした。設備台帳や点検計画書、報告書、故障記録といった保全情報が分散して管理されており、情報の関連付けや活用が困難な状況でした。熟練者の経験に依存した業務体制により、技術継承が困難な状況となっていました。
取り組み
設備保全とキャリブレーション(校正)管理業務を支える新システムを構築しました。設備台帳を軸とした保全情報の一元管理を実現し、点検・報告・故障の各イベントを相互に紐付けることで検索性を高めました。また、製薬工場において非常に重要なデータインテグリティ要件を満たすソリューションを採用し、統制された仕組みを構築しました。
成果
- 過去実績データを活用したPDCAサイクルにより、経験や勘に依存しないデータドリブンなメンテナンスを実現
- 故障履歴、点検計画、結果報告、計測機器校正などの保全データを一元化し、業務の属人性を払拭して標準化を推進
- キャリブレーションの基準書や記録書作成を電子化し、関連する工数を削減
事例の詳細は、以下よりご覧いただけます。
導入事例:住友ファーマ株式会社
これらの事例では、熟練者の経験や勘に頼りがちだった暗黙知を、データとして蓄積・可視化・共有可能な形式知へと変換することで、人材不足や技術継承の課題を克服し、持続可能な設備保全体制を構築しています。両社に共通して見られるアプローチは以下の通りです。
- 1.
-
保全情報の"一元管理"と"可視化"
散在していた設備台帳や保全計画、作業指示書、故障履歴などの情報を統合システム上に集約し、誰もがアクセスできる共有基盤を構築することで、情報の探索時間を削減し、全体像を「見える化」しました。
- 2.
-
現場業務の"デジタル化"と"標準化"
紙や口頭で行われていた点検・作業報告をタブレットやモバイルアプリから直接入力できるようにすることで、現場作業の効率化とデータのリアルタイム収集を実現し、業務プロセス自体の標準化を促進しました。
- 3.
-
データに基づく"予防保全"と"意思決定"
蓄積された保全データやセンシングデータを分析し、熟練者の勘ではなく客観的なデータに基づいた計画的な保全(予防保全)や、故障予測・原因究明を可能にすることで、トラブル対応の迅速化やメンテナンスコストの最適化を図っています。
これらの取り組みを通じて、両社は熟練技術者のノウハウを組織全体で共有・活用し、将来にわたる持続的な成長を実現しています。
統合ソリューション導入による課題解決
これまで解説してきた3つのアプローチを効果的に実現するには、個別のデジタル化施策ではなく、統合的なソリューションの導入が不可欠です。
IoTセンサーからのデータ収集、AIを活用した異常検知・予兆把握、そしてナレッジデータベースによる見える化(BI)、知識体系化といったデジタル技術を統合的に活用することで、熟練者の暗黙知を誰もがアクセス可能な形式知へと変換できます。これにより、組織全体で技術やノウハウを共有し、確実な技術継承を実現できるでしょう。
製造業の技術継承やDX推進において、何から着手すべきか迷われている企業様は少なくありません。エクサでは、EAMソリューション《Maximo》を通じて、数多くの現場での課題解決をご支援してまいりました。「自社に合った進め方を相談したい」とお考えでしたら、お気軽にご連絡ください。
お問い合わせはこちら
オンライン相談会のご予約はこちら
関連する記事
関連ソリューション
関連事例
お問い合わせ
CONTACT
Webからのお問い合わせ
エクサの最新情報と
セミナー案内を
お届けします