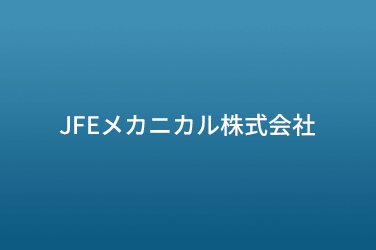製造業の設備保全現場では、熟練技術者の退職や法規制対応の厳格化により、従来の紙ベースの管理手法では対応が困難になるケースが増えています。
業務の効率化や法対応の迅速化といった観点からも、ペーパーレス化の重要性が高まっているのが現状です。しかし、単純に紙を電子化するだけでは、情報の集約や分析による業務改善につながらないケースも少なくありません。
本記事では、現場に定着し、持続可能な改善につながるペーパーレス化の進め方を、成功事例とともに解説します。
設備保全の現場で続く紙管理の課題
多くの製造業では、設備保全業務において点検記録や作業報告書などの情報管理が依然として紙ベースで行われています。この従来の管理手法は、さまざまな課題を生み出し、業務効率や品質向上の妨げとなっているのが現状です。
紙管理による情報分散と業務の非効率化
設備保全では、点検チェックシートや作業報告書、月次報告書など、多くの情報が紙やExcelで管理されており、部門ごとに文書が分散しています。現場担当者が手書きで記録し、それを後からExcelに転記・集計する運用が常態化しており、入力ミスや記録の読み取りミスも起こりがちです。
また、保全情報が異なる形式や保管場所で管理されているため、必要な情報を迅速に取り出すことが難しく、帳票の突き合わせや共有も非効率です。このような属人的な運用は、業務の標準化や引き継ぎにも支障をきたし、保全業務全体の見える化を妨げています。
技術伝承・人材育成への阻害要因
データが分断された状態は、設備保全管理に関わる知見を部門全体で共有する上での障壁となり、技術伝承や人材育成の推進も困難にしています。特に、熟練技術者の退職が進む中、紙ベースの管理では知識の形式知化や標準手順の明確化が進まず、技能の継承が難航しています。また、基準書や記録書の作成、および定められた責任者への承認済み複写書類の印刷・配布・回収に費やしている工数も、生産性向上の妨げとなっています。
特に保全作業においては、紙帳票だけでなくレガシーシステムやファイルに縛られていることが、ペーパーレス化を阻む大きな要因となっています。その背景には、現行業務からの変化に対する不安があります。ペーパーレス化に移行した際に、どの作業が減り、どの作業が新たに発生するのかといった変化点を十分に整理できず、メリット・デメリットを正しく想定・準備できていないことが原因です。
こうした背景から、推進にあたっては業務負荷やプロセスの変化を丁寧に可視化し、現場が具体的に理解できるように説明することが不可欠です。システム部門が一方的に進めるのではなく、業務部門と密接に連携し、二人三脚で進める体制を整えることが、ペーパーレス化を現場に定着させるには欠かせません。
実際の「現場の声」を知りたい方へ。
ペーパーレス化を進めた現場では、どんな変化が生まれたのか?
担当者のリアルな声をまとめた事例資料をご覧ください。
紙管理の限界と"見える化"の遅れ
設備保全における紙ベースの管理手法は、情報の即時性や分析機能において根本的な限界を抱えています。デジタル化が進む現代において、これらの限界は設備の安定稼働や効率的な保全業務の実現に深刻な影響を与えています。
情報集約・分析の遅れがトラブル要因に
紙ベースの管理では、設備の状態把握や異常兆候の検知が遅れ、重大トラブルや生産停止リスクを高めてしまいます。手書き記録による転記ミスや可読性の問題により、正確な情報伝達が困難になっています。
さらに、紙に記録されたデータは蓄積・分析が困難で、過去の故障パターンや劣化傾向を把握することができません。設備の異常兆候を早期に発見し、予防保全につなげるためには、継続的なデータ分析が不可欠ですが、紙ベースではこのような高度な分析が実現できず、結果として事後保全に頼らざるを得ない状況が続いています。
また、複数の設備や部門をまたがる情報の統合も困難で、工場全体の設備状況を俯瞰的に把握することができません。これにより、設備間の関連性や影響度を考慮した総合的な保全計画の策定が阻害されています。
監査対応や報告作業の負担が増大
過去記録を探す、Excelに転記する、帳票をファイリングするなど、管理・報告業務も煩雑化しています。特に、法規制対応や内部監査において必要な証跡を提示する際には、必要な記録を紙資料から探し出す作業には時間がかかり、監査準備の負担が増しています。紙ベースでは記録の検索性が極めて低く、特定の期間や設備に関する情報を抽出するだけでも時間がかかります。また、データの改ざん防止機能や承認履歴の管理も困難で、監査で求められるトレーサビリティの確保が不十分になりがちです。
さらに、報告書の作成においても、複数の紙資料から必要な情報を手作業で集計・転記する必要があり、作業の属人化が進んでいます。これにより、担当者の不在時には業務が停滞するリスクや、引き継ぎ時の情報漏れといった問題も発生しています。
ペーパーレス化を実現させる4つのポイント
紙管理の課題を解決するためには、単純にデジタルツールを導入するだけでは不十分です。現場に定着するペーパーレス化を実現するためのポイントをご紹介します。
1. 業務フローの見直しと目的明確化
単なる紙から電子への置き換えではなく、現場の業務プロセス全体を見える化し、デジタル化の目的を明確にした上で設計を進めることが重要です。
現在使用している点検チェックシート、作業報告書、月次報告書などを全て洗い出し、どの情報がいつ、誰によって、どのように活用されているかを詳細に分析します。特に、情報の流れや承認プロセス、他部門との連携ポイントを可視化することで、デジタル化の対象範囲と要件を明確にできます。
また、紙ベースで行っていた作業をそのまま電子化するのではなく、デジタルの特性を活かした業務フローに再設計することが重要です。例えば、部署ごとに分散していた文書管理を一元化し、紙ベースの承認プロセスを電子承認ワークフローに変更するなど、組織全体の情報共有を効率化する視点で業務プロセス全体を見直します。
2. 現場教育と巻き込み設計
導入目的と現場にもたらす具体的なメリットを丁寧に伝え、現場リーダーを巻き込んだ教育・運用体制を構築することが定着の成否を左右します。
変化への不安を軽減するため、導入前に現場での課題ヒアリングを徹底的に行い、ペーパーレス化がこれらの課題解決につながることを具体的に示します。また、失敗しても大丈夫という安心感を与えるため、紙帳票との並行運用期間を設定し、段階的に移行していくことが重要です。
教育においては、一斉研修ではなく、職種や習熟度に応じたグループ別研修を実施します。実際の業務で使用する帳票を用いたハンズオン形式の研修を中心とし、操作方法だけでなく手順の理由や背景も含めて説明することで、理解度を高めます。
さらに、現場のキーパーソンを早期に特定し、システム設計段階から参画してもらいます。これらのリーダーがシステムの設定作業や同僚への指導を担うことで、現場主導の変革を実現できます。また、成功事例や改善提案を現場リーダーから発信してもらうことで、自然な浸透を促進します。
3. システム選定は"現場視点"で行う
機能が豊富であっても"現場で使い続けられるか"を重視し、長期的な運用を見据えた設備保全管理システムを選定することが重要です。
ITに不慣れな現場担当者でも直感的に操作でき、タブレットやハンディ端末から直接入力できる操作性に加え、情報の検索性や技術の蓄積・共有ができる機能が求められます。
また、これまで紙や口頭、Excelなどで分散していた情報がシステム上で一元管理できることが重要です。設備台帳から図面、マニュアルまで、保全に関するあらゆる情報が相互に紐付けられ、高い検索性を持つシステムが求められます。
導入前には、目的と課題を明確にした上で、プロトタイプを用いて複数の現場担当者が操作を体験し、業務への適合性を確認します。一部の部門に限定した試用期間を設け、PDCAサイクルを回しながら改善点を反映させた後、導入範囲を拡大していくアプローチが効果的です。
長期運用を見据えた選定では、柔軟性と拡張性を備え、他の社内システムとの連携が容易で、カスタマイズなしで要件を満たせる機能が重要です。また、ベンダーの手厚いサポート体制と、蓄積されたデータに基づいて設備の状況を適切に判断でき、熟練者の技術継承を促進しながら、長期的にトータルコストを最小化できるシステムを選定することが求められます。
4.継承と改革
電子化において、現行業務をそのまますべて新しいフォーマットに置き換えることが最適とは限りません。なぜなら、紙帳票は利用目的に応じて(日次・週次・月次・年次など)最適化された書式で運用されてきた経緯があるからです。
ペーパーレス化とは単に「紙の情報を電子データに変換する」ことではなく、「既存の情報を新しい管理手法に沿って効率的に再現する」ことを意味します。そのためには、入力形式や表示のタイミング、活用シナリオを精査し、新しい業務フローに適した形で設計し直すことが重要です。こうした再設計を通じて、従来の紙運用では見えにくかった課題を解決できる点を、現場に理解してもらう必要があります。
成功事例に学ぶ、現場主導での導入アプローチ
設備保全管理システムを活用したペーパーレス化を成功させている企業では、どのような取り組みを行ったのでしょうか。ここでは、西部石油株式会社の事例を通じて、現場に定着する導入アプローチのポイントを見ていきます。
西部石油株式会社:年間3,500件の購買書類を完全ペーパーレス化
設備の保全や検査、部材購買に関するデータが一元管理されておらず、多くの業務がExcelを用いたデータ集計や紙ベースのワークフローによって行われていました。旧システムの機能不足が足かせとなり、組織内での効率的な情報共有が困難な状況でした。
旧システムのサポート終了を機に新たな設備保全管理システムの導入を検討する中で、初期段階からペーパーレス化を重要な要件として位置づけ、設備保全管理を中心とした業務全体のデジタル変革を目指しました。連続稼働を前提とする製油所において、必要な薬品や触媒、添加剤などの部材切れは操業停止という甚大な損失を招くため、購買機能の強化とペーパーレス化は切実な課題でした。
-
定着のための取り組み:
工務部長をオーナーとして保全、購買、予算管理、情報システムの各部門からメンバーを選出し、購買書類のペーパーレス化を中心としたプロジェクト体制を構築しました。約180名のユーザーに対して3週間かけてペーパーレス化の操作教育を実施し、システム稼働時には現地サポートで質疑対応を行いました。
この結果、工事仕様書や見積書など1件あたり約8種類、年間で約3,500件に及ぶ購買資料の完全ペーパーレス化を実現し、紙ベースの承認プロセスを廃止しました。これにより社内のリモートワークが拡大し、多様な働き方の選択を可能としています。また、システムとハンディ端末の連携により、棚卸作業期間を約50%短縮するなど、ペーパーレス化による業務効率化を実現しています。
西部石油株式会社の導入プロセスと具体的な効果の詳細については、以下をご覧ください。
導入事例:西部石油株式会社
麻生セメント株式会社:設備保全の紙帳票をデジタル化
設備の老朽化と作業員の高齢化により熟練者不足が深刻化し、設備保全業務の効率化が急務となっていました。メンテナンス情報が紙文書やExcelファイルなど部署ごとに異なる方法で管理されており、情報の一元化と効率的な共有体制の構築が課題でした。
人材育成においても、従来のOJT中心の手法では限界があり、設備保全や点検、トラブル対応に関する標準化された手順書と情報管理基盤の整備により、必要な情報へのアクセス性向上と業務の標準化を図る必要がありました。
-
定着のための取り組み:
熟練者不足と部署ごとに分散していた情報管理の課題解決に向け、設備保全システムによる客観的なデータに基づく保全業務への転換を推進。現場担当者が自らシステムのテーラリングを行い、現場の実情に合わせた設計を実現しました。基本機能の導入完了後、まず社員が保全関連ドキュメントの共有基盤としてシステム利用を開始し、その後タブレット用モバイルアプリを開発して協力会社も含む現場への導入を段階的に進めました。
この結果、現場担当者がタブレットを使用して日々の設備メンテナンスを行い、作業履歴や設備状態情報を全てシステムに蓄積する環境が整備されました。各設備のメンテナンス担当者に対してシステム上で作業依頼を発行し、作業指示書による具体的な作業内容の伝達、タブレットでの指示内容確認、作業報告書としての結果記録という一連の業務フローを確立。ステータス管理機能により作業進捗の見える化を実現し、依頼担当者が作業の進捗状況を即座に把握できる体制を構築しています。
麻生セメント株式会社の導入プロセスと具体的な効果の詳細については、以下をご覧ください。
導入事例:麻生セメント株式会社
組織全体で推進するペーパーレス化の実現
設備保全の現場に残る紙管理の課題は、情報の分散による非効率だけでなく、技術の継承や監査対応にも影響を及ぼします。とくに熟練者の退職が進む中、知識の属人化を放置すれば、将来的な業務停滞を招く恐れがあります。
こうした状況を抜本的に見直すには、現状の帳票や業務フローを棚卸し、課題の所在を明らかにした上で、改善の方向性を整理することが重要です。現場の実態に即した段階的な進め方が、ペーパーレス化の定着を左右します。
そのためには、現場リーダーを含む教育体制の構築や、現場視点でのツール選定も欠かせません。属人化を防ぎながら、日常業務の中で自然に活用される仕組みを整えることで、ペーパーレス化の定着と継続的な改善を実現できるでしょう。
ただ、「自社に最適なペーパーレス化の進め方が分からない」といった声も多く聞かれます。
エクサは、そうしたお悩みに寄り添い、これまで数多くの現場で課題解決をお手伝いしてきました。現場で培った経験と技術を活かし、貴社の状況に合った解決策をご提案します。 設備保全領域でのお困りごとがあれば、まずはお気軽にご相談ください。
関連する記事
関連ソリューション
関連事例
お問い合わせ
CONTACT
Webからのお問い合わせ
エクサの最新情報と
セミナー案内を
お届けします