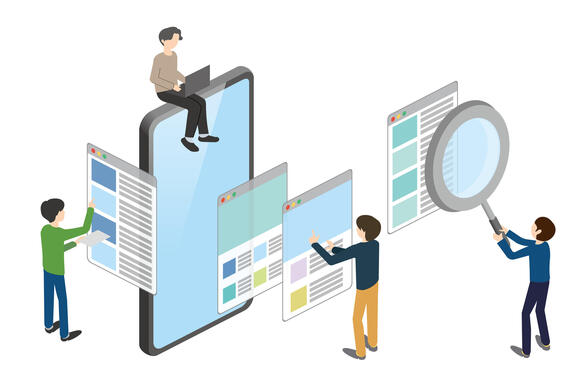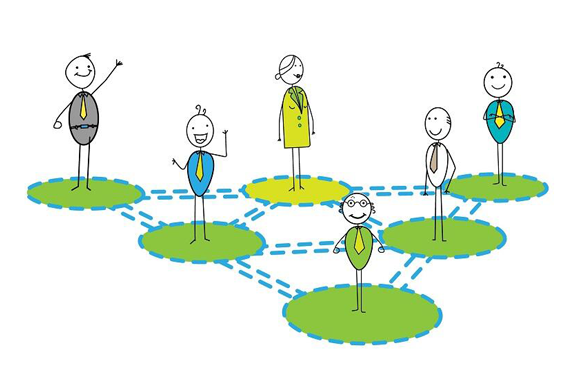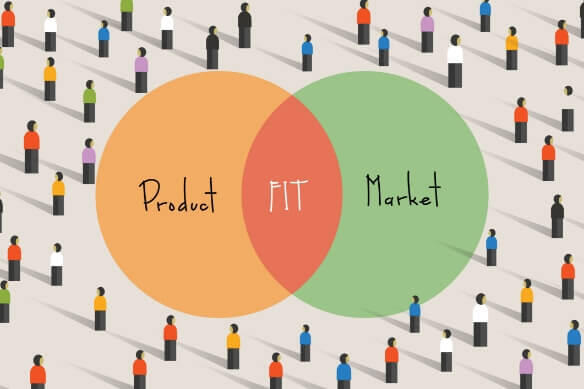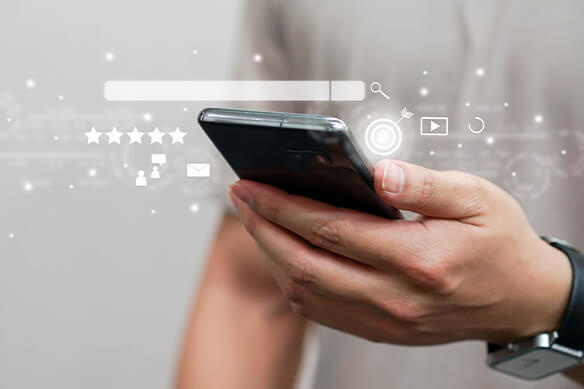製造業において、DX(デジタルトランスフォーメーション)推進は経営課題として避けて通れないテーマとなっています。 しかし、技術導入は進んでいるものの、期待した効果を実感できないケースもあります。その要因の一つとして、DXの基盤となる商品情報の整備・管理が十分でないことが挙げられます。IoTやAIなどの新技術を導入しても、それらが活用する商品データそのものが分散・断片化していては、期待した効果を得ることができません。本記事では、製造業DXにおける商品情報管理の課題とその影響について紹介します。
製造業で DX 推進が進む中、成果が出ない現場も
製造業におけるDXは、今や多くの企業にとって重要な経営課題です。 経営計画に盛り込まれ、IoTやAIなどの技術導入が進み、現場でもスマートファクトリーや自動化の取り組みが始まっています。
しかしその一方で、「DXに取り組んではいるが、売上の増加や業務効率化といった成果につながらない」「他の部門に広がらない」といった悩みを抱えるケースがあります。着手はしているものの、継続的な効果や全体最適には至っていないという状況です。
このような"進んでいるようで進まないDX"の背景には、見落とされがちなボトルネックの存在があります。そのひとつが、商品情報の整備・管理です。
多くの企業では、商品情報が部門ごとに分散し、システム間で一貫性が保てていないという問題を抱えています。
実際に、株式会社Contentservが2023年に実施した「日本の製造業・小売業を対象とした商品情報管理に関する意識・実態調査」があります。
「商品情報管理において、普段の仕事の中で悩み・課題に感じていることをお答えください」(複数回答、n=300)という質問に対し、「情報が複数のシステムやデータベースに分かれている」と回答した企業が39.0%と最も多い結果となりました。
続いて、「部署などスタッフによって利用する情報ソースが異なる」(24.0%)、「マスタ情報の管理や統制ができていない(できているかわからない)」(22.7%)といった回答が上位を占めています。これらはいずれも商品情報の分散・分断に関する課題です。
また、「商品情報管理において誤記載などあった場合、リカバリコストが発生していると思いますか」(単数回答)という質問では、商品情報の誤記載等によるリカバリコストが「発生している」と感じている企業が55.7%に達しています。
これは、情報の分散・分断が単なる業務の煩雑さにとどまらず、実際のコスト負担として企業経営に影響を与えていることを示しています。
このように、調査結果によると、従来は自社特有の問題と考えられていた商品情報管理の課題は、実際には業界全体に共通する傾向であることが示されています。
調査期間:6月1日~15日
調査対象:日本の製造業・小売業の担当者300名(インターネット調査、n=300)
参考:日本の製造業・小売業を対象とした『商品情報管理に関する意識・実態調査』|株式会社Contentserv
分散した商品情報を"営業力"に変える、3社の実例
商品情報管理の課題を、PIMでどう解消したか。
3業界(電子光学/産業機械/精密機器)の各社が選んだ打ち手と、成果をまとめました。
商品情報の管理がDX推進を阻む理由
製造業DXが目指すデータ活用や部門間連携において、商品情報は中核となる重要な情報です。設計、製造、営業、サービスといったあらゆる部門で使われるこの情報が統一されていないことが、DX推進の大きな障壁となっています。本来であれば、部門横断で統一された情報が共有されるべきところですが、実際には、部門ごとに異なる表現・形式・更新タイミングで運用されている企業が多く存在します。
商品情報管理の課題がDX推進を妨げる理由を説明します。
部門分断による連携阻害
商品情報は企業内のひとつの部署では完結しません。設計部門ではスペック情報、仕様書、図面など商品を作る上で必要な情報を管理し、マーケティング部門ではキャッチコピー、商品説明、商品画像など商品を売る上で必要な情報を管理しています。
同じ製品でも設計部門では仕様中心、営業部門では提案資料中心、製造部門では部品構成中心といったように、情報の観点が部門ごとに異なります。この分断により、DXの核となるシステム間のデータ連携が困難になり、全社横断的なデジタル化が進まない要因となっています。
それぞれの部門で情報が生成され、管理されていくため、個別にExcelを用いた管理もあれば、部門の専用システムで管理されているケースもあります。最終的にはそれらに横串を通して管理する必要がありますが、その際は、他部門で管理されている項目を入手し、自部門で管理している項目とくっつけて、重複して保持しているケースも見受けられます。
このような状況では、営業担当者が顧客から製品仕様について問い合わせを受けた際、手元の資料では即座に回答ができないケースが生じます。同じ製品でもカタログとWebサイトで異なる説明がされているといった問題も発生し、その結果、顧客の不信感を招き、ひいては顧客接点のデジタル化を阻害しています。
手作業更新による遅延問題
古い管理手法やシステム利用により、価格や画像、スペック変更などの反映が遅れ、デジタル化による業務効率向上や顧客体験の改善を妨げています。
設計変更や価格改定が発生した際、複数の部門や媒体に情報を展開する作業が手作業中心となるため、反映漏れや時間差が生じやすくなります。特に、Webサイト、営業資料、カタログなど、複数の媒体で異なる情報が表示されてしまうリスクがあり、デジタルチャネルでの一貫した顧客体験の提供を困難にしています。
この情報の不整合は、顧客からの信頼を損なうだけでなく、社内での混乱や業務効率の低下を招き、DX推進における迅速な意思決定や顧客対応の足かせとなります。結果として、情報更新に時間を要し、常に最新かつ正確な情報を顧客に提供することが困難になります。
属人管理による標準化阻害
特定の担当者に情報管理が依存する属人化により、DXの基盤となる業務の標準化・自動化が進まず、デジタル技術の効果を十分に発揮できません。
長年の経験を持つ担当者が個人のExcelファイルで重要な情報を管理している、部門固有のルールやノウハウが文書化されていないといったケースが多く見られます。
このような属人化が進むと、担当者の異動や退職時に重要な商品知識が失われるリスクが生じ、組織全体での情報共有や業務の標準化が進まない要因となります。
また、属人的な管理では情報の品質や精度にばらつきが生じやすく、AIやIoTなどのデジタル技術が前提とするデータの統一性や品質を確保できません。これにより、新しいシステムを導入してもデータの精度にばらつきがあるため、システムを十分に活用できず、DX投資の効果が限定的になってしまいます。
特定の担当者が不在の際に製品に関する問い合わせに対応できない状況や、ベテラン社員の退職時に重要な製品知識の引き継ぎに苦労する状況は、多くの製造業で共有される課題となっています。
DXを進める土台としての商品情報管理
これまで見てきたように、商品情報の分散・分断、更新の遅延、管理の属人化といった課題が、製造業のDX推進を阻む大きな要因となっています。IoTやAIなどの最新技術を導入しても、それらが活用するデータそのものに問題があれば、期待した効果を得ることはできません。
製造業のDXを成功させるためには、技術導入に注力する前に、まず商品情報という「データの土台」を整備することが重要です。商品情報は、設計から製造、営業、アフターサービスまで、企業活動のあらゆる場面で活用される中核的な情報資産です。この情報が正確で統一され、リアルタイムに更新される環境が整って初めて、DXの真価を発揮することができます。
実際に、DXで成果を上げている企業の多くは、システム導入と並行して、または事前に商品情報の管理体制を見直しています。部門を横断した一貫性のある情報基盤があることで、新しいデジタル技術がその効果を最大限に発揮し、組織全体の変革につながっているのです。
商品情報管理は、単なる業務効率化の手段ではなく、DXという大きな変革を支える基盤そのものと言えるでしょう。
商品情報管理の改善に向けた取り組み
商品情報をDXの土台として活用するためには、従来の分散・属人的な管理から脱却し、組織全体で戦略的にアプローチする必要があります。以下では、多くの製造業が取り組んでいる3つの主要なアプローチについて説明します。
商品情報の一元管理体制の構築
製品情報を統合し、設計・生産・販売・マーケティング・アフターサービスなど各部門間で一貫した情報共有を実現することがDX推進の出発点となります。
従来は部門ごとに分散していた商品情報を、全社で共有・活用できる重要な資産として捉え直すことが重要です。一部の製造業では、商品情報を戦略的な経営資源として位置づけ、部門を横断した情報基盤の整備に着手する動きも見られます。
実際に、前述の調査で「商品情報を管理する上で魅力的だと思う機能をお答えください」(複数回答)という質問に対し、「商品データを一元管理できる」が76.7%と最も多く、一元管理へのニーズが高い傾向が示されています。
データマネジメントとガバナンスの強化
データの収集から保管、活用・廃棄までのルールや責任を明確化し、情報資産の適切な管理とセキュリティ環境の整備を進めることが必要です。
新しいシステムを導入する前に、まず「どの部門が何の情報を管理するのか」「情報が変更された時の更新手順はどうするのか」「各部門が使う情報の形式や項目をどう統一するのか」といった基本的なルールを明確にすることが出発点となります。
製造業では、これまで技術や設備に注力してきた企業でも、情報管理の重要性を見直し、データガバナンスの強化に取り組む必要性が認識されつつあります。
PIM導入による業務効率化
複数システムやチャネルに分散しがちな情報を集約し、商品情報のアウトプット業務を自動化・標準化する仕組みとして「PIM(Product Information Management:商品情報管理)」が注目されています。PIMは商品情報を一元管理し、複数のチャネルに効率的に配信するためのシステムです。
実際に導入した製造企業では、数万点に及ぶ部品データの一括更新が可能となり、大幅な業務効率化を実現しています。従来は各部門で個別に行っていた情報更新作業が、PIMにより一度の操作で複数のチャネル(Webサイト、カタログ、営業資料)に自動反映されるようになり、作業工数の大幅な削減を実現しています。
欧米ではPIMの導入が進んでいる一方で、日本では比較的導入が遅れていました。
しかしながら、近年は国内でも導入企業が増え、状況が変わりつつあります。
前述の調査で「あなたがお勤めの会社の『商品情報管理(PIM)』の認知・導入状況をお答えください」(単数回答)という質問を行ったところ、PIMの認知率は38.0%、実際の導入率は13.0%となっており、さらに今後の利用意向を示す企業が34.3%に達しています。
このように、商品情報の分散・分断という課題解決の手段として、PIMという専門的なシステムへの関心が高まっています。
参考:前述の株式会社Contentserv調査より
PIMに関しては、以下の記事をご覧ください。PIMが生まれた背景や活用するメリットを詳しく解説しています。
PIM(商品情報管理)とは?
見落とされがちな商品情報管理の重要性
製造業におけるDXは、単なるシステム刷新ではなく、組織全体の連携や価値提供の在り方を見直す取り組みです。DX推進において、IoTやAIなどの新技術導入に注目が集まりがちですが、多くの企業が見落としているのが商品情報管理です。
自社のDXが思うように進まないと感じている場合、商品情報管理という盲点に目を向けてみることが重要です。調査結果が示すように、他社では既にこの領域への取り組みが進んでいます。
部門ごとに分散している情報、更新タイミングのズレ、属人化した管理体制など、商品情報管理の課題を解決することで、DX推進の基盤を固めることができるでしょう。
関連する記事
関連ソリューション
関連事例
お問い合わせ
CONTACT
Webからのお問い合わせ
エクサの最新情報と
セミナー案内を
お届けします